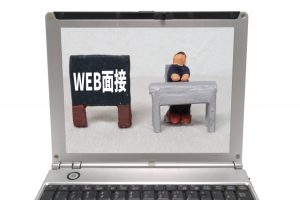4つの失敗事例から学ぶ!プロが伝えるインタビュー取材のコツから記事をまとめる方法

こんにちは歌川です。
質の良いインタビューは出来ていますか?
中途半端な進め方だと、良質なコンテンツは制作できません。
僕はこれまで、地方に根付くお店から、日本を代表するような上場している会社まで、様々な職業の方へインタビューしてきました。
そこで、事前準備が8割と言っていいぐらい重要なのに気付いたんです。
行き当たりばったりの取材スタイルだと、良いインタビューにならずお互いにとってメリットはありません。
その経験から取材のコツと失敗してきたことをお伝えします。
インタビュー取材で失敗したこと

初めに失敗したことからお伝えしていきます。
是非、参考にしてださい。
質問をど忘れしてしまった
当日の会話に盛り上がり、聞くべき質問を忘れたことがありました。
取材後に「あ!聞くの忘れた!」と後悔した経験が。
こうならないため、取材時でも見えるように箇条書きで質問を記載しておきましょう。
取材の日程を勘違いしていた
このようなことがありました。
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”Aさん”]え?明日取材だっけ?[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”歌川”]はい!連絡をしておりますが・・[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”1.jpg” name=”Aさん”]あー!そうだった。忘れたよ(笑)[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”2.jpg” name=”歌川”]・・・[/speech_bubble]
ドタキャンを防ぐために、事前に「〇日は取材でお世話になります」と再度連絡するようにしましょう。
体調を崩した
一番やっちゃいけない、体調不良。
取材の前日は、飲みすぎや夜更かしは控えましょう。
僕は音声と文字の両方で運営しているので、声が出ないなんて死活問題。
どこかで声がおかしい番組があるはずです・・・
■全番組はこちら
良いコンテンツにならなかった
良いコンテンツにならない場合もありました。
インタビューするけど、全然会話にならない。
それは、受け手にメリットが伝わっていないからです。
良い記事にならない可能性が高いのは以下の場合です。
無理な営業
インタビューの押し売りほど意味のないものはありません。
きちんと情報を伝わった人のみ取材するようにしましょう。
知り合いの紹介
紹介は話が早いですが、注意が必要です。
受け手は、紹介してくれた人に信用あるわけで、あなたに興味があるわけではありません。
事前にしっかり伝えて、納得した場合のみ取材しましょう。
自分が興味がない人へインタビュー
これは間違いなく言えます。
あなたが興味がない人にインタビューしたところで、良いコンテンツが生まれるわけはありません。
身内感がでると逆効果
仲が良い人にインタビューすると、どうしても身内感がでて引き出しにくくなります。
見ている方は、「なんか、身内感が出てつまんない」となりがちなので、人選を考えましょう。
その際は、普段関わりのない人や、プロのインタビュアーにお願いするのをおすすめします。
インタビューするまでの事前準備

ここからはインタビューするまでの流れをご紹介します。
冒頭お伝えしましたが、僕はこの準備は8割ぐらい力を入れています。
相手に興味を持つ
インタビューする上で一番大事にしているのが、「相手に興味を持つこと」です。
相手に興味を持てば持つほど、おのずと聞きたいことが頭に浮かんできます。それに、興味を持たれてイヤな気持ちになる人はそうそう居ません。人はどうしても「自分のことを分かって欲しい!」という欲求が強いものなので、しっかり聞いてあげると、話している相手の頭の中の考えもまとまってくるのです。
皆さんも「自分の考えを声にすると頭の中が整理できた」という経験はありませんか?
その経験はきっと悪いことではなかったはずです。むしろ、良い経験になったはず。そしてその経験の中には「聞き上手な誰か」が居るはずです。
逆にいうと、人に興味を持てない人はインタビューに向いていないでしょう。
具体的な事前準備
事前準備するには、間違いなく深い話が出来るからです。
特に有名な方だと多くの情報が出ているので、しっかり調べています。
準備をしないでいくと「いつも同じことを話しているんだけどな」と思われてしまい、せっかくの時間が台無しに。
どのような準備があるか掘り下げておきます。
ネット情報(HP・SNS・過去のインタビュー記事、本など)
受け手の情報はすべて取ります。
先方の素材・資料の送付
事前にどのような質問をするのかを共有しておきましょう。
アドリブでインタビューするのもありですが、それは『事前に準備した質問から面白い方向になったから』です。
何も準備しないで、アドリブに頼るといいインタビューは出来ません。
持ち物
忘れ物はしないようにしましょう。特にレコーダー。
これがないと死活問題です。
日にち・時間の確認
失敗でもお伝えしましたが、特にお一人でスケジュール管理をされている方には、
事前にしっかり確認しましょう。
イメージを作る
事前準備をしっかりすると、会ってもないのに、会って話を聞いた感覚になります。
この感覚までイメージが出来ると、より良いインタビューが出来るようになります。
体調に注意
当たり前ですが、体調管理は必須です。
当日に向けて整えましょう。
インタビュー当日

※ミュージシャンの中村さんインタビューにて
インタビュー当日は、事前準備がしっかりしていれば、何も心配することはありません。
しかし、突発的なトラブルも考えられますのでポイントを押さえましょう。
レコーダーは最低2つは使う
レコーダーで録音する場合は、万が一機材が壊れるかもしれません。
なので、壊れてもいいように2つ以上持つのがおすすめです。
そこまで、機材を増やさないで、一つはボイスレコーダー、もう一つはスマホのレコーダーでも十分です。
僕の場合は、音声でもコンテンツ制作するので、
・マイク等の機材収録機器
・ボイスレコーダー
・スマホ
を使っています。
詳しい機材はこちら
⇒音声番組を始める人は必見!プロが使うおすすめの収録機材「マイク編」
未だかつて収録中に壊れたことはないですが、三つあると安心です。
インタビューのコツ
インタビューでは、この三つを意識すれば想いを届けられるようになります。
過去を聞く
これまでしたきたことは、人となりを知るうえでとても大事な情報です。
「なぜ起業しようと思ったのか?」
「どのような経緯で事業を継いだのか?」
「今まではどのような仕事をしてきたのか?」
過去は歴史です。しっかり過去を聞きましょう。
現在を聞く
今、何に力をいれてるのかを聞くと、リアルタイムの想いを伝えられます。
「どのような仕事をしているのか?」
「どんな人材が必要なのか?」
写真や動画があるとさらに分かりやすいです。実際に任せる仕事が決まっているなら、その流れも伝えましょう。
未来(ビジョン)を聞く
これから何をしていきたいですか?ビジョンを伝えることで、受け手にも伝わり、一緒に働く原動力になります。
相手が話している間に次の質問を考えない。
相手が話しているのに、次の質問を考えたら、今話している内容が頭に入って来ません。
せっかく良いお話をしているのに台無しです。
僕も、事前に進行表は準備していきますが、その場で面白い話があったら、その話を掘り下げるようにしています。
一問一答にしない
質問の答えを掘り下げるようにしましょう。
例えば、
「起業をしたきっかけは?」
「子供の頃の経験ですね」
これで、終わるのではなく、
「その子供の頃の経験をお聞かせください。」
のように、答えに対して深堀していきましょう。
写真を撮る!撮る!
写真はとても大事です。
カメラマンが同席出来れば、必ず同席させるようにしましょう!
一人の場合は、周りの環境と、話している風なシーンをいくつか撮影します。
ポイントをお伝えします。
人を撮る
取材する人の写真を撮るのは必須です。
商品・サービスを撮る
商品やサービスも撮りましょう。
社内環境を撮る
職場の雰囲気も伝えるためにしっかり撮ります。
目的に応じて撮る
その他で、受け手が望む写真も撮るのも必要です。
主導権は必ず取る!
インタビュアーは映画でいうと、『監督』です。
受け手側は『出演者』、それを見ている『観客』。
それをまとめるには、監督であるあなたがすべてを把握して、
目の前の受けてを楽しませるのはもちろん、これを見る視聴者はどう思うか?を考えてまとめることが必要です。
聞きたい質問を見えるようにしておく
話が盛り上がると、聞きたい質問が飛んでしまう場合がよくあります。
そうなったときにでも、すぐに思い出せるようにメモなどを目に付く所に置きましょう。
【最重要】取材後に質問する
これが当日のキモです。
取材だと、受け手はいい意味で身構えますし、すべてをざっくばらんに話せるとは言えない環境になります。
なので、取材後にレコーダーを止めて、一呼吸おいて
「あ、そう言えば、さっき話した○○はどのような意味ですかね?」
とかサラッと聞きましょう、その時に答えたことが、一番の本音です。
そこで、
「面白いですね!本編にも上手く入れ込んでおきます!」
と一言付け加えましょう。
取材後の編集、記事制作

取材後の編集は、コンテンツを制作するにあたり、とても大事です。
より良い記事を制作するたに、押さえておくポイントをお伝えします。
粗々でもいいから2日以内に文字起こし
いくらボイスレコーダーで録音してあっても取材後に日にちが経つと盛り上がった記憶は忘れてしまいます。
なので、粗々でも全体を忘れないようにまとめておきましょう。
先方への確認は必須
当たり前ですが、コンテンツを掲載する前に先方へ確認しましょう。
これをやらないでアップするのはマナー違反です。
編集は目的に応じて変える
嘘でまとめるのはNGですが、同じ取材でも、僕の編集は先方の目的に応じて編集を変えています。
強調したい個所を強めましょう。
例:求人の場合
取材している荒川産業の荒川さんの場合は、求人向けに特化しています。
荒川産業は創業125年続く、巨大グループ企業。
その社長となると新入社員との接点が薄くなります。
そのため、歴史好きなのを前面に出して、番外編として別にコンテンツ制作しました。
自分の考えを入れる
取材はそれだけで客観的なコンテンツになりますが、それを受ける側は距離が遠すぎる場合もあります。
なので、あなたの感想を一文入れましょう。
まとめ
いかがでしょうか。
この通りに制作すれば、質の高いインタビューコンテンツが作れます。
参考になれば幸いです。
■こちらも合わせて読みたい。
⇒集客使える!インタビューのメリットとデメリット
======
■仕事探しで絶対に後悔したくない方へ
インタビュー求人情報
■求職者から60分で3名の応募があった情報発信をしませんか?
[blogcard url=”http://uptory.jp/service/uta-program”]